福音コンサートに感謝です〜ボランティアチームより
岩崎 信
2012年5月20日、快晴。初夏を思わせる日差しでした。この日、パルテノン多摩大ホールで「晴佐久昌英神父と愉快な仲間たち 福音コンサート」が開催され、多摩教会の信者を始め、各地から、900名を超える方々が来場し、午後のひと時をクラシック音楽で楽しみました。私はそのコンサートをお手伝いする事務局のメンバーでしたが、素人だけでこんな大規模なコンサートの運営ができるのかと心配な時もあったものの、神様のお計らいで無事、滞りなく終演。お客様はもちろんのこと、演奏家の方々にも喜んでいただき、運営事務局としては、ホッとしています。
それは、3月1日から始まりました
昨年末からコンサートの話は出ていたのですが、神父様から「福音コンサートを手伝って欲しい。3月1日の晩に集合」と声がかかりました。そして司祭館に集まった私たちに神父様からお話が。「5月20日にパルテノン多摩の大ホールで福音コンサートをやります。司祭に叙階して25年。こうして司祭をやってこられたのも神様と大勢の人たちのおかげなので、みんなに音楽のプレゼントをしたい」…こう言われてお手伝いしないわけにはいきません。集まったメンバーで事務局をつくることになり、加藤泰彦さん、小野原祐三さん、私の3人が運営を担い、演奏家グループを代表して佐藤文雄さんにも参加をお願いしてスタートしました。
まずは、広報活動
事務局がまず行ったのはパフレット作成。加藤さんに動いていただき、この素晴らしいパンフレットができました。このパンフレットを多摩教会始め、神父様がこれまで宣教活動されてきた高円寺教会や高幡教会などの小教区や各所に置いていただきました。
次いで小野原さん担当のホームページ。パンフレットの素材を活用し、昨年末から始まった神父様のミサ説教サイト「福音の村」に掲載しました。そしてお問い合わせの電話は、小野原さんの自宅に回線を引き、奥様の里佳さんに応対をしていただくことになりました。
準備そして、ボランティア募集
紆余曲折の中、何とか準備は進みます。お客様にどのように入場していただくか、そもそもどのくらいの来場者があるのか、長蛇の列ができたらどうしようか。神父様の新著「天国の窓」をどうやって販売するか、などなど。初めてのことですので、みんなで悩みました。そのうち話が膠着状態になり、神父様がひと言「大丈夫。神様がいるんだから、何とかなる」何度この言葉に救われたことでしょうか。そしてボランティア募集。会場担当、書籍運搬、書籍販売の3つの仕事ですが、連休明けから募集したにも関わらず、多摩教会を中心に20名あまりの方々に応募いただきました。
そして当日
書籍運搬は早朝から始め、一箱30冊(30キロ)の段ボールを約50箱、車3台で運び入れました。10時から段取りの説明。その後は会場設営、書籍準備、プログラムのセットなど皆で手分けしてどんどん進みます。
その間、舞台はリハーサル中。たまたまその場に居合わせたのですが、プロの演奏家のリハーサルの気迫たるや、真剣を通り越して鬼気迫るものがあります。納得行くまで、何度も何度も演出家とやり取りがあり、すごいものです。
その一方で、多摩教会福音コンサート合唱団の楽しげなこと。もちろん緊張していらっしゃいましたが、この舞台に立つことを心から楽しんでいるようでした。
11時半から整理券の配布開始。時間を追うごとにお客様の数は増え、12時45分に入場、13時15分に開場。次から次へとお客様が来ますが、混乱もなくスムーズに入場していきます。そして、神父様の「よーこそ、みなさん」で開演です。佐藤さんのピアノ独奏で始まったコンサートは、あっという間の3時間で「乾杯の歌」でクライマックス、そしてアンコールを皆で合唱。
神父様や演奏家の方々と、お客様のお見送りをしましたが、皆さんとても満足そうに、幸せな顔で帰られていて、事務局としてこれに勝る喜びはありません。神様の計らいが福音コンサートに働いたということなのでしょう。
そして、神父様の新著「天国の窓」は300冊近く売れました。来場者の3分の1が買い求めたことになり、これも聖霊の働きでしょう。それとも神父様のセールス力?
その後の打ち上げで、ボランティアの方に感想を伺ったところ「またコンサートのボランティアをやりたい、次はいつですか」という方も。
最後になりましたが、晴佐久神父様、銀祝おめでとうございます。そして素敵なコンサートのプレゼントをありがとうございました。



ボランティアスタッフ( 順不同 )
大窪尚子、吉良元裕、斉藤具子、江口照子、藤塚恵、藤木かおる、和田恭輔、大山正史、山田淳、渡邉顕彦、松岡泰孝、伊禮正太郎、友永廉、奥野悟、大矢むつみ、足立久美子、小川紀子、山藤ふみ、山藤清香、笹田浩子、小俣浩之、神田冨美子、吉瀬美帆子、豊島太一、内藤義明、佐藤文雄、三浦あかね、加藤泰彦、小野原祐三、小野原里佳、岩崎信
◆フォトアルバムで、「福音コンサート」の様子をご覧いただくことができます。ぜひこちらをご覧ください。 







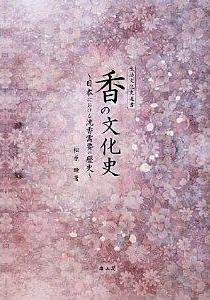 香の文化史
香の文化史